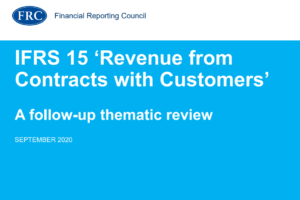日本基準での「のれん償却」をめぐる議論が注目を集めています。
10月2日から4日にわたって、日本経済新聞に「のれん考・識者に聞く」というシリーズが掲載されました。「のれん」の定期償却を定めた日本の会計ルールを見直すべきかどうかの議論に関して、3名の識者の見解が掲載されています。
そのなかで個人的に注目した箇所について、以下に抜粋しておきます。
【ASBJ初代委員長 斎藤静樹氏】
・M&Aで取得した様々な資産のうち、建物や機械設備などの資産は償却するのに、のれんだけ償却しないというのは違和感がある
・超過収益力やブランド価値であるのれんが永遠に減耗しないというのはあり得ない。一定期間で償却するのが合理的だ
・日本の学術界で非償却を積極的に支持する研究者は多くない
・のれんの償却か非償却かを選べるようにするべきだという意見もあるようだが、同じ会計基準に沿って作成されたはずの財務諸表が比較できなくなり、問題がある。中途半端な考え方はよくない
【ブイキューブ社長 間下直晃氏】
・海外基準と異なりのれんを償却する日本基準のルールはM&Aの障害になっている
・将来的には非償却で統一するとして、それまでに10年間など十分な移行期間をとり、その間だけ選択を認めるという形がよいのではないか
・IFRS移行には準備に何年もかかりハードルが高い。
【IASB理事 鈴木理加氏】
・見積もり困難な償却期間に基づく償却では、投資家に有用な情報の提供ができないという問題意識が強かった
・償却モデルを採用する場合、投資家にとって有用な情報は『なぜその期間で償却することをマネジメントが見積もったのか』だ。しかし償却年数は理論的には見積もれるが、実務的にはその背景を開示するコストやリスクは小さいとはいえない
・IFRSは一貫した会計処理を推進しており、オプション(原則以外の選択肢)はできるだけ少なくすることを目指している。会社に選択権を認めても、再度の変更は認められない。その時の最高財務責任者(CFO)らが決めた手法に後の経営陣が納得し続けるのかという問題も出てくる。そういう状況に企業を追い込むのは適切ではない
3名の見解は、まさに「定期償却を支持する斎藤氏」「非償却を支持する間下氏」「非償却を制度化したIASB理事の鈴木氏」という三者三様の立場をよく表しています。
以前からの投稿でも述べているように、のれんの定期償却と非償却にはそれぞれ理論的な根拠があります。どちらかが完全に正しいというよりも、それぞれが異なる目的や前提に基づいて設計されていると考えるべきでしょう。
そのため、現時点では一方が他方より優れていると断言することは難しいと思います。
そのうえで、私見を述べるなら、日本基準についてはこれまでどおり定期償却を維持する方がよいのではないかと考えます。
のれん非償却が明らかに優れているという新しい根拠が提示されたわけではないなかでの変更は理論的根拠に乏しく、日本基準を適用するすべての企業に対して償却方法を変更させるのは、実務面での作業負担や影響があまりにも大きいからです。
IFRSとの整合性を図るのであれば、のれん非償却である一方で、減損の兆候が無くても毎期1回、減損の兆候がある場合には追加で減損テストが求められるため、コストや工数、詳細な開示負担の増加につながる点も忘れてはなりません。
また、定期償却と非償却の「選択制」にする案については、私も斎藤氏や鈴木氏と同様に反対の立場です。
同じ会計基準のもとで企業ごとに異なるルールで財務諸表が作成されるようになれば、比較可能性が損なわれ、会計基準の根幹が揺らぐおそれがあります。
そもそも我が国において、IFRSは「任意適用」です。「NG」でも「強制」でもなく、「任意適用」。つまり、適用する基準自体の選択制が認められている状況です。
したがって、この状況下でさらに日本基準内で選択制を設ける必要性は高くなく、のれんを非償却で処理したい企業は、IFRSを選択すればよいというのが私の考えです。
ここでよく言われるのが、「IFRS導入には少なくとも5年以上の期間を要する」「コンサル報酬が数億円かかる」というような、いわゆるIFRS移行の壁に関する話題です。
そこで、次回の記事では、IFRS移行に際して必要となる期間とコストの誤解について、支援の現場から得たリアルな経験をもとに解説します。