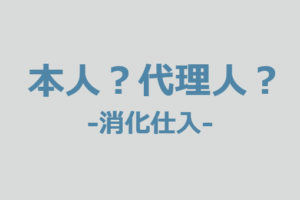財務会計基準機構(FASF)はM&Aで生じるのれん償却の会計処理の見直しについて話し合い、まずはスタートアップ関係者らを対象に、のれんを非償却とした場合の影響などについて聞き取りに着手することを決めたようです。
この度の経済同友会ほか複数の民間団体などからの提案は、①のれんの償却と非償却を認める選択制の適用、②のれん償却費を営業費用でなく営業外費用か特別損失に計上の2点で、①は2027年度までに、②は2026年度までに結論を出すことなどを求めているとのこと。
民間団体などからの声を受けて、いよいよFASFが動き出しましたね。
私もちょうど先日、上場企業に伺った際に、経理担当の方々からのれんの償却について質問を受けました。
これまでものれん償却の議論については何度も投稿していますので、それを読んで概ねの経緯などは把握されていたようですが、今回ののれん償却と非償却の選択制、のれん償却費の計上区分の変更は実際に起こり得るのか、私の見解を聞きたいとのこと。
まだFASFが動き始めた段階で予測するのは難しいですが、私の見解を以下にまとめてみます。
■ 償却と非償却を認める選択制の適用
償却と非償却にはそれぞれ合理的な理由があり、どちらかが一方的に正しいと結論づけるのは非常に難しいです。日本基準でも何度も議論を重ねて現状の償却処理に行き着いており、よほど新しく優れた理論的な根拠がなければ変更されることはないと思います。
今回、複数の民間団体を中心に意見がまとめられたというのは新しい動きのように思えますが、これはM&Aによる償却費負担を軽減させたいという実務的な視点からの提言であり、非償却が優れているという目新しい理論的な根拠が現れたわけではありません。
もっとも、IFRSがのれん非償却という結論に落ち着いた以上、今回の民間団体の声が、国際的な整合性を図るという点で非償却に処理を変更するきっかけとなる可能性は考えられます。
以上より、まず償却から非償却に変更される可能性は半分をやや下回る程度と考えます。
では、選択制ならどうか。
個人的には選択制となる可能性は、以下の理由から非償却に変更されるよりも大幅に低いのではないかと思います。
・選択制とすると、企業ごとにのれんの会計処理が異なることになり、企業間の比較可能性が損なわれる。
・償却か非償却かを選択できると、企業に利益操作の余地が生じる。
・選択制は結果的にIFRSや米国基準などとも異なる結論であり、国際的な会計基準との整合性も図れていない。
私としても上記の理由から選択制という結論には同意しづらく、少なくとも償却か非償却のどちらかに会計処理を統一すべきと考えます。
■ のれん償却費を営業費用でなく営業外費用か特別損失に計上
のれん償却費を営業外費用か特別損益に計上することについて、こちらも以下の理由から、計上区分が変更される可能性は低いと思っています。
・特別損益として計上されるのは、臨時・異常な項目である。減損テストの結果として計上される価値毀損相当分はまだしも、定期償却相当額を特別損益に計上することは、特別損益項目の定義からして考えにくい。
・のれんはいわゆる超過収益力であり、企業の将来的な収益獲得が期待される無形資産的性質のものだという観点から鑑みると、その償却費は営業利益に影響を及ぼすと考えるのが妥当であり、営業外費用として計上することにも違和感が拭えない。
なお、同じ上場企業の担当者から「もし仮に、のれん償却処理や計上区分が変更されることになった場合、いつから変更後の基準が適用されますか」ということも質問されました。
私、占い師とちゃいますから。
あくまで現状での個人的な予測として答えると、以下の理由から早くても2030年頃ではないかと見ています(「そんな先ですか!」と言われましたが、「おそらく、そんな先です!」と答えました。)
・仮に選択制に変更するとしても、減損テストの詳細検討、処理方法を変更する際の制限(一度非償却を選択すると、何年間は償却処理に変更できないなど)、遡及適用の有無、IFRSとの整合性をどこまで図るのかなど、他に検討すべき内容は非常に多い。公開草案にも多くの意見が寄せられるであろう内情を踏まえると、基準の策定には相応の年月を要する。
・2027年に新リース基準の適用があり、多くの上場企業がこの対応に時間を奪われることが想定される。実務的な面から見ても、今から2,3年後の適用は現場に混乱が生じる可能性が高い。
繰り返しますが、この段階で予測するのは難しいというのは百も承知で書いていますので、その点はご留意ください。
実務担当者の方々から、のれんの処理が変わるのかについて質問や問い合わせが非常に多いので、読者の皆さまに向けて書かせていただきました。
今後ものれん償却について動きがあれば、投稿を行っていきたいと思います。