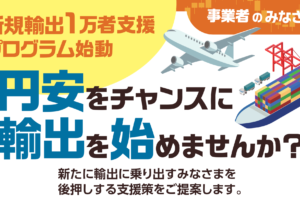一昨日の日本経済新聞朝刊に、不正会計が10年で倍増したという記事が掲載されていました。
当該記事の情報元である東京商工リサーチのホームページには、以下の内容が記載されています。
2020年に「不適切な会計・経理(以下、不適切会計)」を開示した上場企業は58社(前年比17.1%減)、総数は60件(同17.8%減)だった。集計を開始した2008年以降、2019年は過去最多の70社、73件だったが、2020年はそれぞれ下回った。だが、年間では50件台を持続し、高水準の開示が続いている。
2020年に不適切会計を開示した58社の内容は、最多は子会社で不適切会計処理などの「粉飾」が24件(同40.0%)、経理や会計処理ミスなどの「誤り」も24件(同40.0%)と同数だった。
個人的に関心を持ったのは、 不適切会計の割合に、処理ミスのような意図的でない「誤り」も、粉飾と同じく最多の40%を占めているということです。
これには様々な要因が考えられるでしょう。
ビジネスのグローバル化や多角化に伴って会計処理自体が煩雑化・複雑化したこと、あるいは働き方改革や世の中の流れによる労働時間の短縮化によって、会計処理のチェックに時間を割くのが難しくなったことなどあるかもしれません。
しかし、私が危惧しているのは、会計処理の誤りを事前に防ぐ、または事後的に発見する仕組みを構築するためのコストを会社が削減している傾向にあるのではないか、もう少し突っ込んで言うと、経営者が経理部門を軽視していないかということです。
これは、いわゆる内部統制云々の話より前の、組織の根本に係る問題だと思っています。
それを実感した経験があります。
以前、私が経理体制の構築支援などで関与した会社でのこと。
経営者が利益拡大を図って、コスト削減に目を向け始めました。
経営者がコスト削減を考えるのはいけないことではありません。むしろ望ましい。
問題は何のコストを削減するのかです。
私から見て、その会社には削減しても売上拡大や事業運営、従業員の士気などに影響しない、いわゆる無駄なコストがいくつか存在していました。まずはこういう無駄なコストから削減していくのが基本です。
しかし、この会社の経営者は、経理業務のコスト削減に手をつけ始めました。売上獲得に直接的に貢献していないコストだという理由でした。
もちろん私からも経理部門の重要性やコスト削減の考え方などを伝えましたが、忙しいことを理由に理解しようとしてくれません。そのあいだにも経営者は、必要以上の人員削減、著しく価格が安い顧問税理士への変更、会計処理のチェック時間の大幅削減を進めていきます。
こうような方法でも、目先の利益はたしかに増加するかもしれません。しかし、長期的にみると必要なコストを削った反動、つまり経理部門の弱体化というツケが回ってきます。
経理部門の弱体化は、会計処理の誤りが発生する可能性が高くなる、会計監査人の監査に耐えられなくなるといった問題につながるだけではありません。
お金に関する情報を握っている経理部門が弱体化することは、投資と回収のバランスなど金銭的裏付けに基づいた投資意思決定が困難となる可能性が高まる。すると、思うような投資成果が得られず徐々に会社が弱体化し、またコスト削減のために経理部門の予算を削減するという負のスパイラルに陥ってしまいます。
これはあくまで私の経験に基づく一例ですが、このような経験をされた経理部門の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の新聞記事にあるような会計処理の「誤り」の増加を招いた要因の一つに、経理部門へのコスト削減、ひいては経営者による経理部門の軽視といった面もあるのではないか。
もしそうであるなら、会計処理の「誤り」も単なる一時的な不注意で片付けられるものではなく、経理部門への必要以上のコスト削減の結果が招いた、いわば起こるべくして起こった「人災」なのかもしれません。
このような状況を減らすべく、今後も経理部門の重要性を説くとともに、望ましい経理体制に近づけるための支援を、私自身も微力ながら行っていきたいと思います。