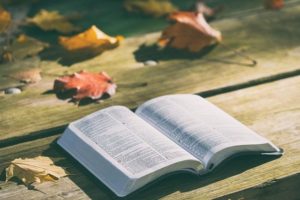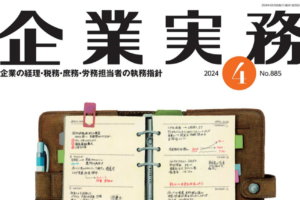今朝の日本経済新聞朝刊に、欧州連合(EU)が企業のサステナビリティー情報の開示規制を緩和する方向に転じた旨の記事が掲載されています(以下、記事より一部抜粋)
欧州連合(EU)が企業のサステナビリティー情報の開示規制を緩和する方向に転じた。適用を遅らせたり適用範囲を縮小したりする方針だ。欧州に進出する日本企業にとって負担が軽減する見込みで、企業からは歓迎する声が聞かれる。半面、脱炭素の取り組みが遅れる恐れもある(中略)
日本の規制議論にも影響する可能性がある。金融庁はサステナ情報の開示を27年3月期から時価総額3兆円以上の大企業に義務づけ、最終的には東証プライム全社に適用する考えだ。だが「産業界からプライム全社に広げるのはやり過ぎだとの意見が出ている」(監査法人パートナー)。
欧州連合の方向性が日本の規制議論に影響する可能性があることは、これまでの流れを見てもその通りだという認識です。あとは我が国におけるサステナ開示をどのように義務付けていくかという方向性ですね。
記事にあるように、時価総額で一定の基準を設けて、開示の必要性の有無を分けたり、段階的な導入を行うこともあるべき一つの方法だと思いますが、それに加えて実務担当者の作業負担の軽減を前提としながら開示内容について簡素化の方向で進むことを個人的には期待しています。
これまで開示の実務にも関与してきた私の考えは従来より一貫していて、企業が有報などで開示する内容や、法律等で開示が義務付けられる情報量は現状でも多すぎると思っています。まずは開示内容を削減して経理担当者に空き時間を作る。その生まれた時間で、企業の数値情報から現状および将来性に関する分析を行う。そして、企業価値向上につながる経営者の行動を、経理担当者らが情報面からサポートしていくという方向に、経理担当者の役割をシフトしていったほうが良いと思っています。