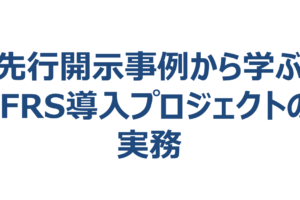のれん償却の議論が続くなかで、よく耳にするのが「IFRS移行の難しさ」や「導入コストの高さ」に関する話題です。
前回の投稿「のれん償却をめぐる議論と私見 ー 日本基準は定期償却を貫くべきか」で紹介した株式会社ブイキューブ社長間下氏の指摘のとおり、たしかにIFRS移行には一定の準備期間が必要となるでしょう。
先日行われたのれん公聴会でも、別の参加者から「IFRSへの移行に際し、コンサルタントへの導入コストが数億円単位で生じる」旨の発言がありました。
この点、IFRS導入支援を数多く行ってきた私の経験からすると、こうした内容は現在の実務感覚とは少しかけ離れているように感じます。
私がIFRS導入支援を始めた2011年当時は、まだIFRS適用企業がわずか3社程度で、先行事例もほとんどなく、移行に5年や7年を要することも珍しくありませんでした。
しかし今では、先行事例が増え、開示のフォーマット関係も整い、会計監査人やコンサルタントのノウハウも蓄積されてきており、スタートアップを含む多くの上場企業で、2年から3年程度で移行可能な環境が整ってきています。実際、私が直近で支援した上場企業の中には、1年で導入を完了したケースもあります(資料作成や会計監査人との協議などかなりハードなので、ここまで短期間での導入はオススメしませんが)。
長期化している企業に共通していると感じるのは、ゴールに直結しない資料作成や会議が多すぎることです。
私が支援時に推奨している「ゴール逆算方式」では、最終目的から逆算して本当に必要な作業を明確化するため、無駄なステップを大幅に削減できます。これにより、限られたリソースでもより短期的なスケジュールで導入を進めることが可能となります。
また、コンサル報酬についても「数億円かかる」というのは、あくまで一部の大企業に限られる話でしょう。大半の企業では、社内体制の整備と外部支援の適切な組み合わせによって、現実的なコストで導入が進められます。
IFRS導入を検討するうえで大切なのは、はじめから「時間がかかる」「コストが高い」と決めつけないことだと思います。企業の目的や体制によって最適な進め方は異なり、正しく設計すれば負担を最小限に抑えることができます。
このように、IFRSに移行する際のハードルは確実に下がっています。のれんの非償却やIFRSへの移行を検討している企業こそ、誤解や過去のイメージ、一部の声にとらわれず、現場を知る専門家の意見を聞いて判断していただきたいと思います。
IFRS導入やコスト、実際の支援内容について関心のある方は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。
現場で得た知見をもとに、貴社の状況に合わせた具体的なご説明をさせていただきます。