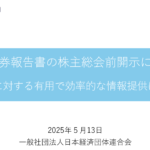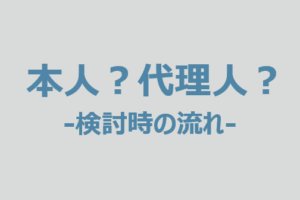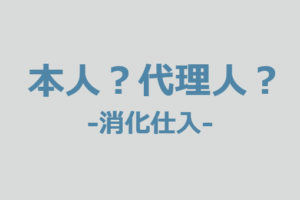今朝の日本経済新聞の一面に、大きく「M&A「のれん」償却不要」という記事が掲載されています(以下、一部抜粋)
企業がM&A(合併・買収)する際、「のれん」の償却を定期的にしない会計処理を認める制度変更の動きが出てきた。会計上の負担を軽くしてスタートアップなどのM&Aによる成長を後押しし、企業の新陳代謝を進める効果が期待できる。
(中略)
日本基準を採用する企業は償却費を毎年計上する分、決算書上の営業利益が小さくみえる。M&Aの買収価格ものれんの償却費を考慮した上で提示しなければならないため、他国企業との競争に不利となりやすい。
(中略)
経済同友会が2023年に会員の経営者らを対象に実施したアンケート調査によると、7割超の企業がM&Aを検討する上でのれんの償却費が障害となっていると回答した。
(中略)
こうした状況を踏まえ、首相の諮問機関である規制改革会議がのれんの会計処理について「非償却」または「非償却か償却の選択制」に変えることを答申で提起する。日本の会計基準を定める企業会計基準委員会(ASBJ)に検討を要請する。
まず最初に一言。新聞記事の表題は「M&A「のれん」償却不要」となっていますが、まだ要請段階であって、現時点でASBJから当該内容に関するコメントなどは公表されていませんので、ご留意ください。
というわけで、先日の投稿「「のれん償却は成長の足かせ」という記事と今後の方向性への私見」でも取り上げたように、のれん償却に関する議論が国内で再燃しています(というか、程度の大小はあれ、ずーっと燃えている)。
なかなか落ち着きませんね。
今回の記事では、「経済同友会が2023年に会員の経営者らを対象に実施したアンケート調査によると、7割超の企業がM&Aを検討する上でのれんの償却費が障害となっていると回答した」とあります。つまり、のれんは償却すべきでないと考えている関係者が多いと。
一方、同じ2023年にASBJが公表した活動報告の資料には、いまや懐かしい修正国際基準に触れたうえで、「IASB(国際会計基準審議会)とFASB(米国財務会計基準審議会)は償却の再導入の検討をやめているが、ASBJは、国内の関係者の多数が現在でものれんは償却すべきと考えていると認識しており、意見発信を継続する予定である」と書かれています。
はてさて、事実やいかに。
また、記事ではのれんを償却すると営業利益が小さく見えるうえに、他国企業との競争上不利となる点からも非償却が良いとのこと。
否定はしません。が、
のれんを償却しないと、のれんの残高が積み上がって貸借対照表に占めるのれんの割合が膨大となり、それ以外の資産の実態がよく分からなくなってしまうので償却すべきだって話、どこ行きましたっけ?
米国ではのれん非償却の結果、純資産の50%を超えるのれんが計上されている企業がおよそ4割、100%を超えている企業が5社に1社もあるってのが、つい最近まで問題提起されていたのでは?
これを受けて、IFRSや米国基準でものれんは償却すべきだと大きな議論になったのが、ほんの3年ほど前。
我が国でもこれに賛成して、IFRSも日本基準のように償却すべきだと盛り上がっていたのですが、今度は日本基準でもIFRSのように非償却にすべきだと大きな声が上がる。
やっぱり落ち着きません。
今回の要請を受けて、ASBJがどのように対応するんでしょうか。
ちなみに、IFRSの設定主体であるIASBは2022年11月、のれんについて償却の再導入をこれ以上検討しないことを決定しています。
のれん償却の話が記事になるたびに、実務の現場で経営者や担当者からどうなるんですかと不安そうな顔で聞かれます。影響の大きな論点ですからね。
現場の混乱を防ぐためにも、日本基準でも一度決めたら当面は変えないくらいの決意で検討を進めていただきたいと思います。