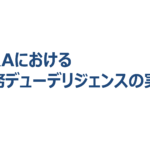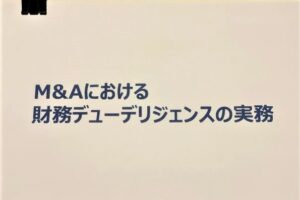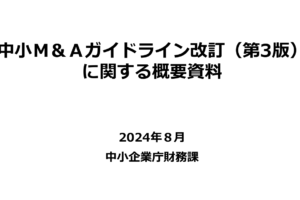今朝の日本経済新聞に、「中小M&A仲介、新資格 来年度にも」という記事が掲載されています(以下、当該記事より一部抜粋)。
中小企業庁は中小企業のM&A(合併・買収)を手掛けるアドバイザー資格を2026年度にも創設する。仲介者に財務や法務の知識と実務能力を求める。中小のM&Aでは悪質な仲介を繰り返す事業者もいる。事業承継の需要が高まるなか、売買時のトラブルを防ぎ、市場の活性化を促す。(中略)
米国ではM&A仲介事業者の自主規制団体が仲介の認定資格制度を運営している。資格の取得には筆記試験のほか、一定の実務経験が必要になる。資格は定期的な更新が必要で、自主規制団体のホームページで保有者を検索できる。
中小企業庁の公表データによると、我が国のM&A件数は増加傾向にあり、近年では年間4,000件前後と過去最高水準で推移しています。
件数が増えればトラブルも増えるということで、ここ最近、M&Aの仲介事業者が関係するトラブルについて、特集が組まれたりニュースで頻繁に報道されたりしているのは、読者の皆さまもご存知のとおり。
「資格も不要なためサービスの質の差が大きい」、「売手・買手よりも自社の利益を優先している」といった仲介事業者への不満や苦情が、件数の増加に伴って顕在化してきたということなのでしょう。
もちろん、本当に悪質だといったケースもあるのでしょうが、仲介事業者にも得意としている業種や規模などがあり、報酬面も含めて事前の契約内容の確認やお互いの認識のすり合わせ不足がトラブルにつながったという事例も多いのだと思います。
とはいえ、中小企業の経営者にとって、M&Aは人生に一度あるかないかの大きな意思決定。
これはM&Aの仲介事業者を選定するときに限った話ではありませんが、中小企業の経営者に伝えたいのは、マイホームを購入するときに現地に足を運ぶのと同様、専門家と対面で会って話して、この人なら安心して相談できる、任せられるという人を自分自身が納得して選ぶのが大事だということです。
専門用語がわからなければ、専門用語がわかる専門家と一緒に話を聞けばいい。
これだけでも、契約後のトラブルに巻き込まれる可能性を軽減できると思います。