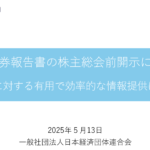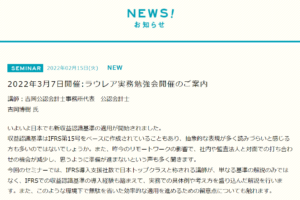本日の日本経済新聞に、一橋大学の野間幹晴教授による、「のれん償却は成長の足かせ」という記事が掲載されています。
日本におけるスタートアップの出口戦略は新規株式公開(IPO)に偏重しており、今後スタートアップへの投資を増やし、成長を促すためには、欧米のようにM&Aを増やすことが欠かせないが、その障害となっているのが、日本の会計基準における「のれん」の定期償却という会計処理である旨が記載されています。
そのうえで、日本基準におけるのれんの会計処理の見直しの方向性として、①のれんの償却を廃止すること、②償却と非償却の選択制にすることを提示し、今後のれんの会計処理について議論が深まることを期待したいとして記事が締められています。
のれんを償却か非償却の選択制にするなどと聞くと、目新しい議論や方向性のように感じる方もおられるかもしれません。しかし、実は同じように、2023年4月の日本経済新聞でも「M&Aの阻害要因となるのれんの規則的償却は見直すべきだ」「償却か非償却か選べるようにしてほしい」という記事が掲載されていました。
当該記事に関する私見は、その際の投稿「日本基準での「のれん償却議論」に関する私見」を読んでいただくのが早いと思います。
今回の記事にあるように、のれんの定期償却がM&A増加を妨げる要因になっているという点は私も同意です。
もっとも、日本の企業において日本の会計基準の適用が強制されているならまだしも、現状はのれんを定期償却したくなければIFRSを適用するという選択も可能です。
私自身がこれまで数多くIFRS導入支援を行ってきた経験から述べると、IFRS導入時および導入後に生じるコストや作業負担は、先行適用事例が豊富になってきたこともあって以前より軽減されてきたように感じます。また、特にスタートアップの段階では、大企業のように事業規模や従業員数も多くなく、IFRS導入で盛んに大変だと言われる開示面への対応も、そこまで過度に負担と考える必要はないと思います。
ですので、コストや作業の負担とのれん非償却のメリットを比較して、のれん非償却のメリットが大きければIFRSを適用するといった選択をすればよいのではないでしょうか。
また、3年ほど前にIFRSがのれんを償却するか非償却とするかで活発に議論がなされた際、日本からはIFRSでも日本基準と同様に償却すべきだとの声が大きかったように思います。
にもかかわらず、今度は日本基準がIFRSに合わせてのれんを非償却とするというのは、いささか腰が据わっていないのではないかと。会計処理の変更は現場に混乱をもたらすということも考えておく必要があるでしょう。
次に、のれんの償却と非償却を選択制にするという話ですが、今回の記事ではIFRSと日本基準でのれんの会計処理が異なると財務諸表の比較が難しくなる旨が記載されています。
のれんの償却と非償却を選択制にした場合、同じように財務諸表の比較が難しくなりませんかね。
これまではIFRSか日本基準かで明確に処理が分かれていたものが、同じ日本基準内で処理が分かれるとなると、余計に財務諸表利用者の混乱を招く気がします。何かこれを解消するお考えがあるということなんでしょうか。
いずれにしても、のれんの償却議論はどちらの言い分も一理あって、なかなか終わりが見えません。
個人的には、賛成反対もさることながら、他の実務家や学者の方々がどのような考えを持っているのか参考にできることもあって、このような記事は非常にありがたく、今回も興味を持って読ませていただきました。
そして、その一方で、会計処理に関する議論や投稿によって、経営者や経理担当者ら実務者が過度に振り回されることのないよう、私自身も意識や配慮を持っていきたいと思います。